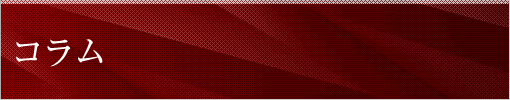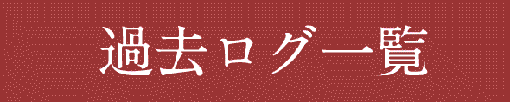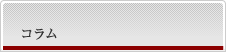生前贈与に関する最高裁判決の意義
武富士元会長から長男への海外資産の生前贈与に関する最高裁判決
結構大きい最高裁判決が出たと思います。
この判決を受けて、日本の富裕層がどのように動くのか、今後の動向を注目しておく必要があるでしょう。
消費者金融大手「武富士」(会社更生手続き中)の故・武井保雄元会長夫妻から海外法人の株を生前贈与された長男の武井俊樹元専務(45)が、贈与税など約1330億円の課税処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は18日、課税を適法とした2審判決を破棄し、処分を取り消した。判決は「元専務は当時、海外を生活拠点としていたため課税できない」と判断した。個人に対する追徴課税取り消しでは過去最高とみられる。
(中略)
訴訟では元専務の生活拠点の認定が争点となった。贈与時(99年)の相続税法は、海外居住者が国外財産の贈与を受けた場合は非課税と規定。元専務は97~00年の3分の2を香港で過ごしたが、国側は、課税逃れの海外滞在で実質的な生活拠点は国内と主張した。
これに対し、小法廷は「滞在日数という客観的な要素で決めるべきだ」と判断。「税回避目的で海外滞在日数を増やしていたとしても、当時の法律では課税は違法」と述べた。
1審の東京地裁(07年)は「国内に生活拠点があったと認定するのは困難」と処分を取り消したが、2審の東京高裁(08年)は「税回避目的で海外に出国して滞在日数を調整しており、課税は適法」と判断していた。【伊藤一郎】『毎日jpH23.2.18より』
世間では過払い金返還請求の原資に還付金を充当させるべき!といった報道がされています。これは税理士が議論する問題ではないので触れません。
ポイントは3つ。
- 相続税・贈与税を回避するために海外に「住所」を移そうとした富裕層がいた(る)
- 「滞在日数」により「生活拠点」を認定した
- 最高裁は租税法律主義を厳密に適用した
過去の話ではない
平成23年度税制改正で相続税の増税が予定されています。いわゆる『相続税の大衆化』です。基礎控除が40%削減され妻一人・子一人でご主人が亡くなった場合、従来7000万円だった基礎控除が4200万円に減額される予定となっています。
あわせて、相続税の最高税率が50%から55%に引き上げられる予定です。
富裕層にとってこの5%の税率アップは大きなインパクトがあります。
たとえば、上場会社の創業者のように100億円規模の財産を持っている人であれば、5億円の増税!増加税額は全体からしてみれば微々たるもの?かもしれません。しかし、全額にすると55億円になってしまうわけです。
これら富裕層は何を考えるかといえば、武富士元会長のように子供に財産を無税で相続させる方法があるならば行いたいということになるわけです。
何も富裕層に限らず一般的な思考といえるでしょう。
今回の判決では、過去にそのような相続税法の抜け穴があった!という議論ではありません。現在は当時よりもやりにくくなった、ということに過ぎません。
巨額の財産を有する富裕層は今でも何とかできないものか!とプライベートバンク等を駆使して考えているはずなのです。
現在でも海外に住所と財産を移転すれば相続税を回避できる
上記のような抜け穴を塞ぐため、相続税法は平成12年改正で以下のように変更されました。

ご覧頂くとわかるとおり、被相続人(贈与者)と相続人(受贈者)ともに5年超日本国内に「住所」がなければ、日本で課税することができないことになっています。
確かに改正前よりも課税を回避しにくい制度となりました。
しかし、巨額の財産を有する富裕層が高額の相続税を回避するために国内の住所を持たないようにしないとはいえません。
しかも、今回の最高裁判決では、「住所(生活の拠点)」の認定を「滞在日数」により判定すべきであるとしたのです。従来より、中国駐在員が中国による全世界所得課税を回避するためにパスポート上の入出国記録を管理していますが、同様のことを日本の相続税課税を回避するために資産家が行ったら合法!と最高裁がお墨付きをつけたとも理解できるわけです。
諸外国では、相続税のない国が多数存在しています。さらに、現在相続税がある国でも、相続税を廃止しようとする動きがあるようです。タックスヘイブンに逃避した資産を呼び込もうといった思惑もあるようです。
日本から脱出した資産家がこれら相続税のない国に「住所」を設定したら、日本の相続税をまるまる節税できてしまう。そこまでする人がどれだけいるかが問題ですが、恐らく何人かはいますよね。
国内に資産があれば日本に課税されますので、不動産を売却して金融資産に切り替え国外で運用する、そんな時代になってしまうのでしょうか!?
考えすぎだといいのですが。。。